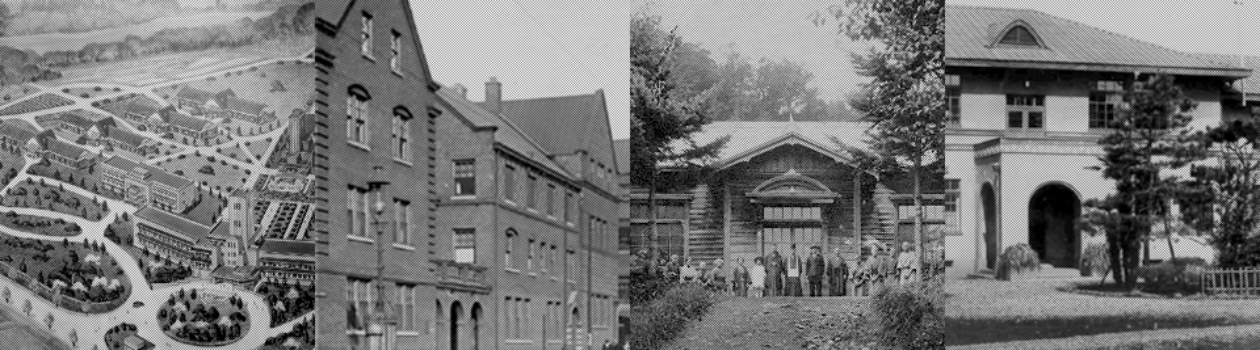●2017年度会費納付のお願い
株式会社ガリレオより会員の皆様に会費納付のお願い通知が届いていると思います。
まだお振込みいただいていない会員の皆様は、早めに今年度会費(8,000円)をお振込みください。
会費の振込口座は、口座記号番号01730-8-125532です。
>会費に関するお問い合わせはこちら
●理事 および 監事選挙 について
2017 年度は社会事業史学会の理事および監事選挙の年度にあたります。後日ご案内 する 「社会事業史学会「社会事業史学会理事およ び監事選出規則」「投票要項」をご確認 のうえ、所定の期限までに 投票頂きますようお願い申し上げます。今回からオンライン投票を実施する予定です。役員選挙は、本学会にとって重要事項ですので、棄権をせず投票されますよう重ねてお願い申し上げます詳細は後日お知らせします。
>社会事業史学会理事および監事選出規則はこちら
●機関誌『社会事業史研究』への投稿について
機関誌『社会事業史研究』の投稿先は下記の通りです。
〒700 -8516 岡山市北区伊福町2-16 -9 ノートルダム清心女子大学
杉山博昭研究室気付『社会事業史研究』編集委員会
研究室TEL:086-252-2169
E-mail:sugiyama[at]post.ndsu.ac.jp [at]を@に置き換えてください
●機関誌の編集業務について
これまで機関誌の編集業務が一部の会員の負担となっていたことから、編集業務の外部委託を視野に入れた機関誌発行のあり方ついて検討してきました。その結果、『社会事業史研究』第51号より、編集・販売の業務を近現代資料刊行会に委託することとなりました。
>近現代資料刊行会はこちら
●住所変更・退会の申し出について
2016 年 5月以降、本学会の会員管理と会費管理を、株式会社ガリレオに委託することになりました。 所属変更、住所変更、メールアドレスなどの 個人情報は、株式会社ガリレオのSOLTIというシステムを通じて会員が直接web上で変更きます。 どうぞご活用ください。
>会員管理はこちらから
●第 36 回社会事業史文献賞の推薦について
社会事業史文献賞は、本学会員の研究の奨励と質の向上を図ることを目的として、1982年度より授与している賞で、受賞者には総会において会長より賞状と副賞( 20 万円)が授与されます。
今回の推薦(自薦を含む。以下同じ。)対象は、2016 年 4月から2017年 3月に発刊(公表)された文献です。推薦に際しては、「社会事業史文献賞推薦用紙」を用いてください。推薦の締め切りは、2017 年 10 月 31 日(消印有効)で、送付先は社会事業史学務局宛でお願いします。昨年度、推薦が0件で「該当者なし」となりました。 文献賞にふさわしい研究書をぜひご推薦ください。
>社会事業史文献賞の推薦要領はこちら
●第 9回吉田久一研究奨励賞の推薦について
吉田久一研究奨励賞は、社会福祉史研究の質の向上、進展を図るため、社会福祉史研究の分野で活躍することが期待される研究者を奨励することを目的とするものです。受賞者には総会において学会より助成金(刊行費助成100万円、研究費助成最高30万円)が授与されます。応募にあたっては、応募要項に従って必要書類を作成してください。応募の締め切りは、2017 年 12 月 7日(消印有効)で、送付先は社会事業史学会事務局宛でお願いします。昨年度、応募 0件で「該当者なし」となりました。研究者を奨励する他の学会にはない制度です。会員の皆様奮ってご応募ください。
>応募要項はこちら
●社会事業史学会第 46 回大会のお知らせ
開催日時:2018年 5月 12 日(土)~ 13日(日)
開催地:東洋大学白山キャンパス
共通論題テーマ: 「東アジア諸国(もしくは国内外)における社会事業史研究の動向 (仮) 」
●第 9回若手研究者交流会のお知らせ
社会事業史学会第46回大会1日目(2018 年 5月 12 日)に開催する予定です。