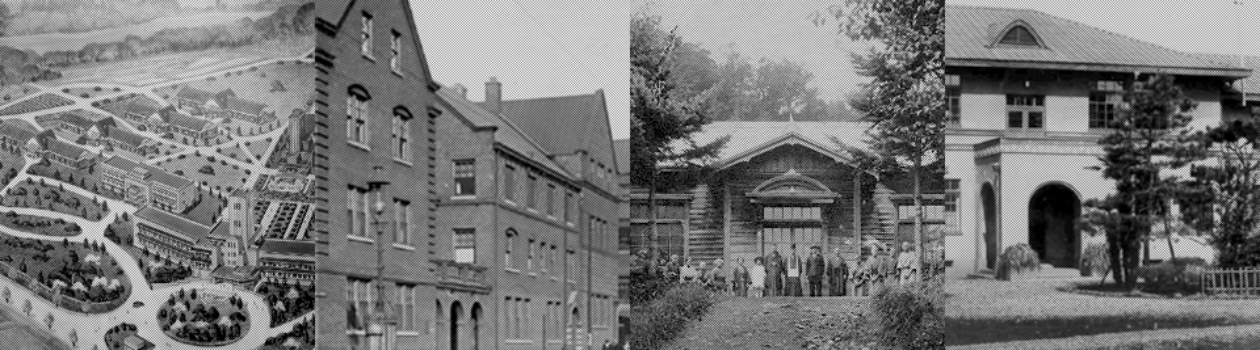「戦後70年目の8月15日によせて」と題する社会福祉系学会会長共同声明が出されました。左のバナーの「声明」にも掲載しましたのでお知らせいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「戦後70年目の8月15日によせて」
1 戦後70年の節目にあたる本年、自衛隊法、PKO協力法、周辺事態法、船舶検査活動法、特定公共施設利用法、国家安全保障会議設置法、武力攻撃事態法、米軍行動関連措置法、海上輸送規制法、捕虜取扱い法の10の法律改正をその内容とする「平和安全法制整備法案」および新たな「国際平和支援法案」の審議が進められている。これらはすでに昨年の集団的自衛権についての閣議決定に沿ったものであるが、従来の自国防衛から、「存立危機事態」へも対応でき、外国軍の後方支援も可能な「積極的防衛」への経路が、国民の安全や他国からの脅威を理由に広げられつつあるといえる。湾岸戦争時に「カネは出すが血は流さない」と国際社会から非難されたともいわれたが、今回の法案は「血を流す貢献」を可能にする環境を整えるものと考えられよう。だがこうした「積極的貢献」が、ある国をめぐる脅威の抑止力になりえるかどうかは、世界の各地で、今日も続けられてきている戦争の実態から、冷静な判断が必要である。
これらの法案が現行憲法に反し、法治主義をゆがめることについては、憲法学者を中心とした批判がある。ここでは社会福祉学の立場から次のような危惧を表明したい。1.どのような正義の名の下においても、いったん始められた軍事活動は、それが「後方」支援であろうと、同盟国への支援であろうと、そこに巻き込まれた国々の人びとの命と日常生活を一瞬にして奪い、孤児や傷病・障害者を増やすだけでなく、それらの深い傷跡が、人びとの生活に長い影響を与え、しばしば世代を超えて受け継がれていく実態がある。2.子ども、障害者・病者など「血を流す貢献」ができない人びとが、こうした事態の中で最も弱い立場に追いやられる。また民族や性別、階層の分断や排除が強められ、テロ等の温床にもなる悪循環が作られていく。3.これらから生ずる「犠牲者」への援護施策とそのための財政その他の社会的コストは一時的なものではなく長期に要請されることに特に留意したい。戦後70年経ってなお、戦争犠牲者への援護行政が続けられ、またそれを巡ってアジアの諸国との対立が続いていることがその一端を示している。4.財政再建を理由に社会保障・社会福祉費の削減が続いている今日、もし「積極的貢献」の負担増がこれに優先するようになれば、少子高齢化が深まる日本の社会福祉の未来は、更に暗いものとなろう。
2 他方で、日本社会福祉学会『社会福祉学研究の50年―日本社会福祉学会のあゆみ』(2004)所収の論文「戦後社会福祉の総括」において、著者阿部志郎氏は、戦後社会福祉が「戦時の「万民翼賛体制」のもとでの厚生事業との断絶があり、国家主義の否定の上に、戦後の民主的な社会福祉が到来したと認識しがちである」とし、自らも含めて日本の社会福祉が戦争責任を自覚してこなかったし、「アジアの国々はもちろん、沖縄さえ視野におさめていなかった」ことを深く恥じていると率直に告白されている(p7~8)。その点が、ボランティア運動でさえ「罪責感」を基礎に再出発した戦後ドイツの社会福祉との「決定的相違」だとも強調されている(p8)。私たちは、この阿部氏の告白をあらためて真摯に受け止める必要がある。社会福祉は、一方で一人ひとりの生活に寄り添いながら、同時に「多数の正義」の名の下での支配体制に容易に組み込まれる危険を孕んでいる。このことに社会福祉研究者は常に自覚的でありたい。
3 日本社会福祉関連の各学会は、90年代より国際交流を活発化させ、特に東アジア3カ国ネットワークの実現に向けて努力してきた。また留学生への支援も強化しようとしている。こうした交流の中で、社会福祉の今日的課題の共通性とともに、文化・歴史的背景の違いについての理解も深められている。「戸締まり」に気を配るだけでなく、国を超えた共同研究や実践交流の積み重ねの中で、相互理解を深めていくプロセスをむしろ大事にしたい。残念ながら、最近の政治的「緊張」が、こうした地道な相互理解の努力に水をさすことがある。しかし、回り道のようでも、緊張を回避していく別の回路を模索することが、学会や研究者の役割であり、国際的な社会福祉研究の水準を高める上でも意味があると考える。
戦後70年目の8月15日を迎えるにあたって、社会福祉研究者・実践者として私たちは、「血」ではなく「智」による、「抑止力」ではなく「協力」による未来社会を展望する努力を続けることを誓い合いたい。
2015年8月15日
日本社会福祉学会会長 岩田正美
日本医療社会福祉学会会長 岡本民夫
社会事業史学会会長 大友昌子
日本ソーシャルワーク学会会長 川廷宗之
日本看護福祉学会会長 岡崎美智子
日本仏教社会福祉学会代表理事 長谷川匡俊
日本福祉教育・ボランティア学習学会会長 松岡広路
貧困研究会代表 布川日佐史